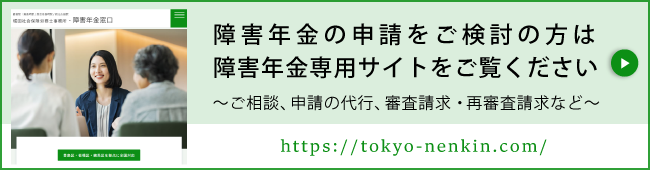Aさんは、精神疾患を患っている方で、お問い合わせをいただいた時には、初診日から10年以上経過しており、通院していた病院がすでに閉院しておりました。カルテも破棄されており、受診状況等証明書の取得が不可能な状況でした。
Aさんの健康保険の診療履歴を利用し、初診日を特定しました。そして当時を知る知人2名がいらっしゃいましたので、その方々にご協力をいただき、第三者証明を作成、無事障害基礎年金2級を受給することができました。知人の方々が大変協力的で、今でも感謝しております。

障害年金のご相談
障害年金とは、約100種類の病気やケガが原因で、日常生活に支障がある場合に一定の条件を満たしていれば、国から支給される公的年金です。
障害者手帳を持っている、持っていないに関係なく受給できる可能性があります。認知度が低く、もらい忘れている人が非常に多い制度です。
人工透析を受けている方、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方など幅広い病気(障害)が対象となります。ほかにも多くの病気が対象となります。年金がもらえるのは「重度の障害を持っている人だけなのでは?」と思われがちですが、多くの病気(障害)が対象となるのです。
障害年金の受給額は、初診日に国民・厚生・共済のどの保険に加入していたか、1級から3級のどの等級に決定したか、配偶者やお子さんの人数によって全く変わってきます。
障害年金制度は非常に複雑で難しいものです。また、ある程度決まったフォーマットにただ入力していけばいいというものでなく、100人いれば100通りの申請方法があり高度な専門性と経験が必要な業務となります。
当事務所では豊富な実績がございますので、お気軽にお問い合わせください。
疾患名の一例を掲載いたします。
| 目 | 白内障、緑内障、ブドウ膜炎(内眼炎)、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮 、網膜色素変形症、 糖尿病網膜症、脳腫瘍など |
| 聴覚 | メニエール病 、感音性難聴 、突発性難聴、 頭部外傷または音響外傷による内耳障害など |
| 鼻腔機能 | 外傷性鼻疾患など |
| そしゃく・嚥下機能 | 舌癌など |
| 言語機能 | 喉頭摘出術後遺症、上下顎欠損、上顎癌(上顎がん)、喉頭腫瘍、脳血栓など |
| 肢体 | 脳卒中、脳出血、脳梗塞、脳腫瘍 、くも膜下出血、分娩麻痺、痙性対麻痺、HAM、 多発性硬化症、パーキンソン病、重症筋無力症、関節リュウマチ(人工関節)、 脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、脊椎管狭窄症、大腿骨骨頭壊死、 変形性股関節症 、球脊髄性筋萎縮症、ALS、ギランバレー症候群、腕神経叢損傷 、糖尿病壊疽、膠原病、骨肉腫 、上肢または下肢の離断または切断 、外傷性運動障害 、ビュルガー症 など |
| 精神 | 統合失調症、てんかん、認知症 、躁うつ病、うつ病(自殺願望)、うつ病(入院) 、うつ病(自宅療養)、高次脳機能障害 、ウイルス性脳炎 、知的障害、広汎性発達障害など |
| 呼吸器疾患 | 気管支喘息(気管支ぜん息)、慢性気管支炎 、肺線維症、肺結核 、間質性肺炎、じん肺 、膿胸など |
| 心疾患 | 狭心症 、心筋梗塞、心筋症、人工弁疾患 、ペースメーカー疾患、 ブルガダ症候群、大動脈解離 など |
| 高血圧 | 高血圧性心疾患、悪性高血圧症、肺動脈性肺高血圧症 など |
| 腎疾患 | 慢性腎炎、ネフローゼ症候群 、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析 |
| 肝疾患 | 肝硬変、多発性肝膿瘍 、肝癌(肝がん)など |
| 糖尿病 | 糖尿病性と明示されたすべての合併症 など |
| その他の部位 | 悪性新生物(がん)、乳癌(乳がん)、胃癌(胃がん)、子宮頸癌(子宮頸がん)、膀胱癌(膀胱がん)、直腸癌(直腸がん)、HIV感染症(エイズ)、人工肛門、直腸膀胱障害 、 再生不良性貧血、白血病 、周期性好中球減少症、脳脊髄液減少症、その他難病や疾患など |
参考事例をいくつかご紹介いたします。
Bさんは、化学物質過敏症を患い、日常生活に大きな制約を抱えている方でした。特定の化学物質(香料や洗剤、建材に含まれる成分など)に触れると、強い頭痛や倦怠感、呼吸困難に陥り、外出すら困難な状態に陥っていました。これにより仕事を辞めざるを得なくなり、障害年金を申請しましたが、不支給となり弊所に問い合わせをいただきました。
当時の申請書類を確認したところ、病状や日常生活への影響が十分に記載されていないことが原因と分かりました。そこで、生活状況を詳細にヒアリングし、具体的な症状や生活の制限内容を病歴・就労状況等申立書に反映しました。また、主治医が作成した診断書には、化学物質に対する過敏性が医学的に詳しく記載されていました。その結果、3級の障害年金が認定され、Bさんは、「少しでも経済的な安心が得られ、生活環境を整えることができました。」と安心した様子でした
当時の申請書類を確認したところ、病状や日常生活への影響が十分に記載されていないことが原因と分かりました。そこで、生活状況を詳細にヒアリングし、具体的な症状や生活の制限内容を病歴・就労状況等申立書に反映しました。また、主治医が作成した診断書には、化学物質に対する過敏性が医学的に詳しく記載されていました。その結果、3級の障害年金が認定され、Bさんは、「少しでも経済的な安心が得られ、生活環境を整えることができました。」と安心した様子でした
Cさんは、慢性疲労症候群を患い、極度の疲労感で日常生活を送ることが困難になっている方でした。短時間の作業でも強い倦怠感が生じ、仕事を継続することが不可能になっている状態でした。ご自身で障害年金の申請をしましたが、症状が見えにくい病気であることから初回の申請では不支給となりました。
私はCさんとお話をし、主治医に再度申請に必要な診断書の作成をお願いするようにいたしました。診断書には、具体的な症状や疲労の度合いを客観的に示すために、医療記録や日常生活の影響が詳細に記載してありました。また、病歴・就労状況等申立書では、ご本人が日常的に行えない活動(買い物や掃除、長時間の外出など)を丁寧に書き加えました。その結果、3級の障害年金が認定され、Cさんは「これで生活が少しでも安定し、治療に集中できます。」と安心された様子でした。
私はCさんとお話をし、主治医に再度申請に必要な診断書の作成をお願いするようにいたしました。診断書には、具体的な症状や疲労の度合いを客観的に示すために、医療記録や日常生活の影響が詳細に記載してありました。また、病歴・就労状況等申立書では、ご本人が日常的に行えない活動(買い物や掃除、長時間の外出など)を丁寧に書き加えました。その結果、3級の障害年金が認定され、Cさんは「これで生活が少しでも安定し、治療に集中できます。」と安心された様子でした。
Dさんは、関節リウマチを患い、長年の炎症で手足の関節が変形し、歩行や物を掴む動作が困難になっている状態でした。治療を続けていましたが、症状が進行して日常生活にも大きな影響が出るようになりました。
主治医が作成した診断書には、Dさんの関節の状態や可動域の制限が具体的に記載してありました。病歴・就労状況等申立書では、家事や移動、仕事でどのような制約があるのかを詳細に記載しました。これにより2級の障害年金が認定され、Dさんは「生活の負担が少し軽くなり、治療に専念できます。」と安心された様子でした。
主治医が作成した診断書には、Dさんの関節の状態や可動域の制限が具体的に記載してありました。病歴・就労状況等申立書では、家事や移動、仕事でどのような制約があるのかを詳細に記載しました。これにより2級の障害年金が認定され、Dさんは「生活の負担が少し軽くなり、治療に専念できます。」と安心された様子でした。
Eさんは幼少期からてんかんを患い、薬で発作を抑えていましたが、大人になってから発作頻度が増加し、突然の意識消失や転倒により仕事や日常生活が危険な状態になっていました。
診断書には発作の頻度や種類、日常生活でのリスクが記載されていました。また、Eさんが単独で行えない作業や就労制限について申立書で具体的に示した結果、2級の障害年金が認定されました。Eさんは「これで転倒事故への備えができ、安心感を得られました。」と話されていました。
診断書には発作の頻度や種類、日常生活でのリスクが記載されていました。また、Eさんが単独で行えない作業や就労制限について申立書で具体的に示した結果、2級の障害年金が認定されました。Eさんは「これで転倒事故への備えができ、安心感を得られました。」と話されていました。
Fさんは転倒による大腿骨骨折をきっかけに手術を受けましたが、その後も関節の可動域が制限され、歩行が困難な状態でした。常に杖や歩行器が必要で、外出や日常生活の一部で介助が必要でした。
主治医が作成した診断書には骨折の後遺症や関節の可動域、日常生活での困難さが記載されていました。また、Fさんが単独で行えない動作を申立書に具体的に反映した結果、3級の障害年金が認定されました。Fさんは「リハビリに集中する余裕ができた。」と感謝されました。
主治医が作成した診断書には骨折の後遺症や関節の可動域、日常生活での困難さが記載されていました。また、Fさんが単独で行えない動作を申立書に具体的に反映した結果、3級の障害年金が認定されました。Fさんは「リハビリに集中する余裕ができた。」と感謝されました。
障害年金申請Q&A
障害年金は、病気やケガなどで障害を負い、日常生活や仕事が難しくなった場合に受け取れる公的な年金制度です。国民年金や厚生年金に加入している人が対象で、一定の条件を満たす必要があります。
1.初診日の確定
初診日は、障害年金の資格要件を満たすための基準日です。この日が正しく証明できないと申請が認められません。
2.障害の程度
医師の診断書を基に、障害等級が判断されます。診断書は傷病によっていくつかに分かれており、該当の診断書に、日常生活や就労状況がどの程度制限されているか等、具体的に記載される必要があります。
3.保険料納付状況
初診日までに一定期間、保険料を納付している必要があります。
初診日は、障害年金の資格要件を満たすための基準日です。この日が正しく証明できないと申請が認められません。
2.障害の程度
医師の診断書を基に、障害等級が判断されます。診断書は傷病によっていくつかに分かれており、該当の診断書に、日常生活や就労状況がどの程度制限されているか等、具体的に記載される必要があります。
3.保険料納付状況
初診日までに一定期間、保険料を納付している必要があります。
•健康保険の記録
保険証を使用して受診した履歴が記録に残っている場合があります。
•お薬手帳や処方箋
初診時の医薬品の処方記録があれば有効です。
•第三者の証言
知人や友人、当時の医師からの証言書(第三者証明)も証拠になります。証明する人によって必要枚数が異なります。
保険証を使用して受診した履歴が記録に残っている場合があります。
•お薬手帳や処方箋
初診時の医薬品の処方記録があれば有効です。
•第三者の証言
知人や友人、当時の医師からの証言書(第三者証明)も証拠になります。証明する人によって必要枚数が異なります。
はい、一定の条件を満たせば過去5年分まで遡って受給することが可能です。ただし、診断書や証明書類の準備が必要です。
障害者手帳は必須ではありません。障害年金の支給は手帳ではなく、医師の作成する診断書や障害の程度によって判断されます。